

「そもそも僕はハリウッド映画に憧れてずっとアメリカで映画を学んでいたんですが、日本に帰ってきた理由が“自分が日本人であること”を知り、“日本人としてのルーツを見直したい”、ということでした。最初は自分のことをよく知らないまま向こうにいたんですけど、外に出れば出るほど“日本人であることのアイデンティティ”を問われる機会が増えて…。まわりのみんなは答えられるんです。でも自分はそこでなにも答えられなくて恥ずかしいという思いをずっとしてきた。で、アメリカで勉強することも大事だけれど、さらに先に進むためにはまずそこを払拭しなくては、日本というモノに面と向かわなければ、と思ったんです。そして帰国し、出会ったのがこの川端康成先生の『古都』の映画化のお話でした。川端先生の文学の世界にガッツリ向かい合い、しっかりと身を寄せるのは自分が願っていたことそのものだし、ここを超えたら絶対そのあとにまたなにか見えてくるものがあるはずだ──と。自分にとって『古都』は長編商業映画第一作で、周囲には「ずいぶん難しい題材だね」とよく言われ…実際、完成まで3年という時間がかかってしまいましたし、難しいのは承知していた。でもまたとない機会、僕は将来のためにもこのテーマをしっかりやり遂げたかったんです。なので、こうしてその結果が一本の映画作品としてつながったのは…感無量です」
「そうですね。作品の世界観を構築するために極力余計なものは削りました」

「もともと最初の20稿くらいまでは小説の世界を現代に当てて書いていたんですけど、小説が書かれたのは50年前で、どうしても現代との時代背景のズレが生じてしまう。実際、世の中から失われていったモノも多いですし、小説にあるファンタジーな要素を現代のリアリティにしたときのギャップにもスゴイ迷ってて…。さらに、二十歳の姉妹を演じ、『古都』という作品を背負える二十歳くらいの女優さんもなかなか自分の中で見出せなくて。で、あるときこの話をあの千重子と苗子のその後と言いますか、ふたりが母になってそれぞれに娘がいるという設定にするのはどうだろうと思い至ったんです。そうすれば母の視点から過去の小説の時代の回想も描けますし、娘の葛藤も描ける。今ここにある伝統をいかに次の世代にバトンタッチするか、という僕が一番やりたい部分もしっかりと描くことができますし」
「はい。ある種小説の後日談を創るということですからね。なので財団のほうへお願いにうかがったところ、“わざわざ若い監督が『古都』を撮るということに興味がある。小説と映画は違うのだから、逆に自由にやってくれないと困ります”と大変有り難いことをおっしゃっていただいて。ただひとつ約束したのが、“川端文学の精神は継承していって欲しい。それがなんなのかは監督としてあなた自身が見つけてください”ということでした。精神は目に見えませんからね。川端先生が美しいと感じたもの、作品に込めたその精神をどう映像化するのかが、僕にとって最大のテーマになったわけです」

「当然自分でも勉強はしますが、京都で撮ると決めたとき、自分の浅はかな知識で勝負することは絶対無理だと思ったので、最初から素直に“わかりません”“教えてください”という精神で行くことにしたんです。そうすると、向こうもスッと中に入れてくださって、いろいろ教えてもらえました。執筆中はまずはなにごとも自分の体験から始まりました。お茶をやってみたり、町家に実際に住まわれているかたのお話を聞いたり。そうして身を寄せていくたびに感じたことを脚本に加えながら、計50稿くらい書き直したんですけどね。そのうち自分でも“いつ終わるんだろう”って(笑)。準備している期間が長くなるうちに“これ、撮るんだよね?”って半信半疑に。とにかく川端康成先生の小説の世界も京都という場所もすごく深すぎて、つかみにかかるんだけど、どこまでいってもつかめきれない。これはいつ着地して、いつ映画のカタチになるのかっていうゴールがしばらく見えない期間が続いたのは、苦労と言えば苦労でした。『古都』の映画化。どういうカタチが正解なんだって言うのを本当に模索して模索して…脚本を書き上げるのに2年間かかりましたが、それくらいの時間をかけなければたどりつけなかった脚本です」
「と同時に、松雪泰子さんの顔が浮かびました。松雪さんだったら母となった千重子と苗子としてこの作品を背負ってくれるんじゃないか、と。松雪さんは…僕がハリウッドから帰ってきて日本での映画創りのやり方の違いなどにとても悩んでいるとき、たまたま『フラガール』を観たんです。そのときに“これ、僕が学んできたこととまったく変わらない! ムービーと映画は違うと思っていたけど一緒なんだ”と感じて、ぱっと目の前の道が開けた。作品に励ましてもらったんですね。特に劇中でとても輝いていた女優さん、松雪泰子さんとはいつかお仕事したいというのもひとつの目標になりました」

「自分のこれまでの経緯や映画に対する思いをしたため、だからあなたで映画を撮りたいという、監督から女優さんへのラブレター(笑)。そうしたらお手紙を読んだ松雪さんが「やる」とお返事をくださったんです。そこから急に状況が現実味を帯びてきて、一気に現場が動き出しました。まさに彼女のキャリアと存在がこの映画を後押ししてくれて…本当に感謝しています。松雪さんは脚本段階からいろいろ意見をくださったんですよ。実際に母親でもありますし、千重子や苗子の思い、女性ならではの心情だとか“母からの視線”というところはもう素直に松雪さんに相談して、時間を取ってもらってマンツーマンで長い時間お話しさせてもらいました。そうやって事前にしっかりコミュニケーションをとれたことで、実際のタイトな撮影スケジュールの中でもしっかり信頼関係が結べていたのかな、とも思っています」
「嬉しいですね。個人的には父親が中学の教師をしていたので、親孝行といいますか…親が望んでいたであろう教師にはなれませんでしたが(笑)、まさかこうして映画で教育関係に関われるとは、ホントに光栄です。日本の、そして京都の伝統を継承していく物語『古都』。僕はこの伝承のお話を、最後は娘たちの世代に問いかける、投げかけるカタチで終わらせたかった。そしてそれを観ている方たちも、伝統を残すというのはどういうことなのかと考えるきっかけになったなら、この映画を創った意味があるのかなと。そこにお墨付きをいただけたのは、かなり大きいことだと思っています。それと僕らは京都の先行上映にもこだわっていて。やっぱりまず京都の人たちに認めてもらってからじゃないと、日本でも世界でも胸を張って“これが京都の映画です”とは言えないですからね。もともと世界へと発信していく前提ですすめていたプロジェクトに国からのお墨付きもいただけた。京都のみなさんにも観ていただけた。ちゃんとした評価を持って世界に出て行けることも非常に誇らしいです」
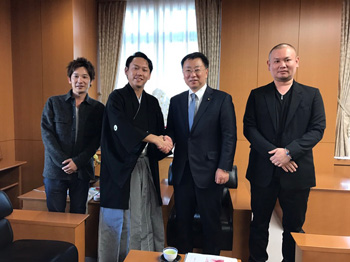
「今まではわりとエネルギーを放出するタイプの作品を撮ってきたんですけど、『古都』は抑える演出で引き算で撮ってきたので…抑えるということは、感じたことが自分の中に溜まってるんですよ。温故知新、過去を見つめつつ自分の作品を撮り切ったことで得たモノは、また別のカタチで次からの作品に生かしていけるはず。まぁ…まずはこの『古都』がお客様の前に出たときが、僕の本当の意味での監督人生の始まり。このインタビューが終わったら、東京の最初の観客が待っている──今、ようやく映画人としてのスタートラインに立てたことを実感しています」
Writing:横澤由香/Photo:小林修士(kind inc.)

MOVIE
絶賛公開中!
pagetop
page top